戎神社、西宮港
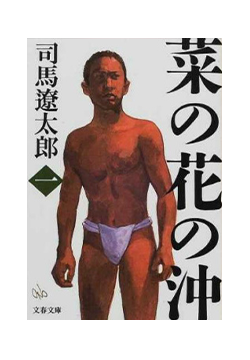
あらすじ:
『菜の花の沖』の主人公、高田屋嘉兵衛は1769(明和6)年、淡路島都志本村(現・兵庫県洲本市五色町都志)に生まれ、寛政2年(1790年)、22歳の時に叔父の堺屋喜兵衛を頼って兵庫に出てきた。堺屋は兵庫と因幡や伯耆を結ぶ廻船問屋を営んでおり、嘉兵衛は、大坂(大阪)と江戸の間を航海する樽廻船の水主(かこ)となった。
寛政4年(1792年)には、同じ淡路出身の「おふさ」と所帯を持ち、兵庫西出町に居を構えた。
優秀な船乗りとなった嘉兵衛は、西廻り航路で交易する廻船問屋として、海運業に乗り出した。28歳で、当時国内最大級の千五百石積の船「辰悦丸」を建造し、当時寂しい漁村にすぎなかった箱館(函館)を商売の拠点とした。
ちょうどその頃、毛皮を求めて千島列島を南下してくるロシアへの国防対策を急ぐ幕府に協力して、エトロフ島クナシリ島間の航路を発見したり、新たな漁場を開くなど、北方の開拓者としても活躍した。
やがて、ロシアとの交易を幕府が拒絶したことから、報復の連鎖反応が始まった。嘉兵衛にも、両国の軋轢が重くのしかかってきて、ついにロシア船に囚われ、遠くカムチャツカに拉致されてしまう。苦難の中、嘉兵衛はロシア軍人との交渉に挑み、もつれにもつれたロシアと日本の関係を独力で改善しようとするのだった。
作品より引用
摂津西宮は、江戸期の都市規模でいえば、堂々たる地方都市であった。
兵庫と大坂の中間にあるが、海港としては兵庫よりも大坂の河口港である安治川尻に近いだけ商業的な結びつきが濃い。
京都とは、陸路西国街道でむすびついている。京都から伏見、淀にくだる道が、天王山のある大山崎で西方へまがり、北摂の山地のふもとの野を通りつつはじめて海浜に出るのが西宮である。
まことに、交通の要衝といっていい。
あまりに要衝でありすぎるというので、幕府はこわくなったらしく、かつては尼崎藩領であったのを、嘉兵衛がうまれた明和六年(1769年)にとりあげて、天領にした。
天下大乱の場合、西国大名が海路侵入して西宮に上陸すれば、京・大坂はのどくびをおさえられたのも同然になる。
とでも、たれかが献言したのだろうか。
(「菜の花の沖 一」p.178)
ただ、商業港としての摂津西宮には、兵庫にはないつよみがある。地場に産業をもっていることであった。
「なんといってもここには酒という強味がある」
と、嘉兵衛はおふさにいった。
造り酒屋は諸国にあるが、良質の酒を均一的に、かつ多量につくる能力は、摂津がもっともすぐれていた。
摂津でも、海岸の西宮からずっと内陸に入った池田や伊丹が、酒造においてすぐれていた。
灘の繁栄は、池田や伊丹よりあとである。
ついでながら、西宮もそのなかにふくまれる灘というのは、大坂湾北岸の一地域名である。ふつう、東は武庫川河口から西は湊川の河口までの五里のあいだをいう。
(「菜の花の沖 一」p.184)
おふさは浜で嘉兵衛をさがしたが、見あたらない。
(もう、お船に乗ってしまったのか?)
とおもい、昨夜そこで逢った灯明台をめざして歩いた。道は、一足ごと砂利に足をとられて歩きにくかった。
灯明台は海中に二十間ばかり石垣が組まれた先端にある。
ここからは、八艘の樽船のうち宝喜丸がいちばんちかい。
淡路島が見えるほどの晴天ではなかったが、空は十分にあかるい乳色で、東風が間断なく吹きつづけている。
(中略)
おふさはぼっと煙るような色白の顔をしているくせに、一人でいるときは小舟をあやつる漁師のように活溌な行動をする。嘉兵衛が浜のどこにも見えないとわかると、すぐ灯明台から離れ、さらに浜を去り、戎の宮へ行って嘉兵衛の無事を祈った。
(「菜の花の沖 一」p.201)
おふさは旅籠をとっている。あすは新酒が出るとうので、西宮の宿という宿ははちきれるような人を泊めていた。このため旅籠で二人が逢えるというわけにいかない。
出典:司馬遼太郎全集第42巻 菜の花の沖 一 文藝春秋
初出:産経新聞1979年から掲載開始 1982年 文藝春秋から単行本刊行開始




